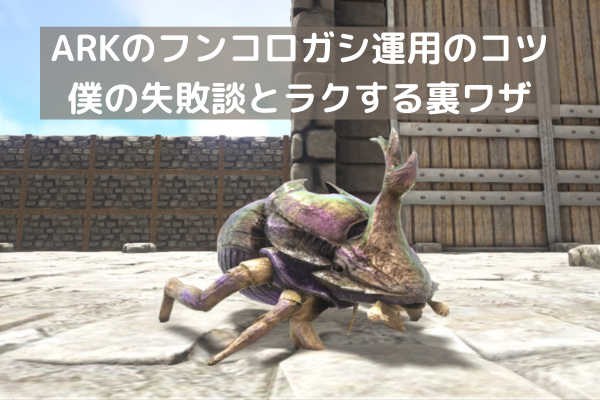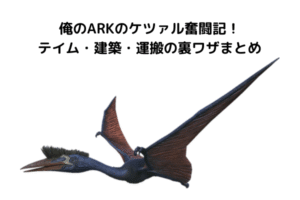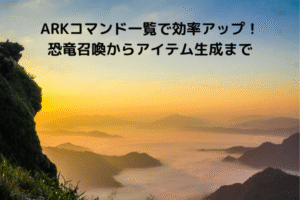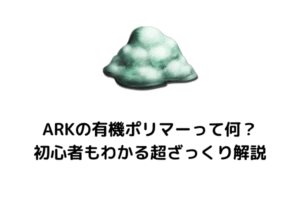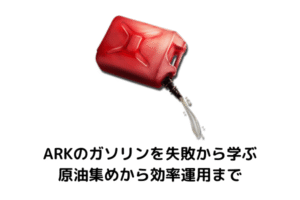ARKのフンコロガシの運用、実はちょっとしたコツが山ほどあるって知ってましたか。
肥料作らない時の焦りやステ振りの迷い、自動採取や放浪モードの便利さと困りごと、そして餌や囲い、場所や持ち方に悩むのは誰もが通る道です。
僕も初めてテイムに挑戦したとき、持てないトラブルや囲い選びでかなり苦労しました。
それでも工夫次第で快適なARKライフが手に入ります。
これから、僕がリアルに経験したARKのフンコロガシ管理のあれこれを、初心者にも分かりやすく語っていくので、一緒にラクな運用法を探していきましょう。
・ARKのフンコロガシを効率よくテイムし飼育する実践的なノウハウ
・放浪モードや自動採取など機能別の運用ポイント
・囲いや設置場所、餌管理など日々の運用トラブルの解決策
・ステ振りや持ち方で後悔しないためのリアルな体験談とコツ
ARKのフンコロガシと私のリアルな日常
・テイムで感じた難しさと工夫
・自動採取の便利さと使いにくさ
・餌選びに迷うことのリアル
・ステ振りで後悔した体験談
・肥料作らない場面で焦る気持ち
・囲いを作る時に注意したポイント
・場所選びで失敗した話
テイムで感じた難しさと工夫
ARKでフンコロガシを初めてテイムした時、「あれ、思ったよりシビアじゃん?」って感じた人、多いんじゃないですか。
僕も最初は完全にナメてたんです。
何しろ、テイムのやり方がちょっと特殊で、攻撃も麻酔も要らない受動テイム。
でもね、これが意外と手こずるんですよ。
まず、アイランドの死の山洞窟やサウスケイブ、ラグナロクの砂漠洞窟、アベレーションの中層区域……どこも敵がゴロゴロいるんです。
「洞窟、入るだけで冷や汗もんだな」とか思いながら、必死に周りの敵を片付けて、ようやくフンコロガシにたどり着く。
それでも気は抜けない。
背後からしゃがんでそ~っと近づいて、インベントリに「大型フン」と「腐った肉」両方セットして、スロットから手渡しですよ。
特に大型フンを優先して使うと、進みが早くて助かるんですが、「腐った肉」だけだと進行が遅くなりがち。
敵に見つかる、こっちも焦る、何回かやり直して「これ、下調べ大事だな」と痛感しました。
それからは必ずフンを複数用意してから出発するようにしています。
「テイムは準備と慎重さが命」、これが僕のモットーです。
自動採取の便利さと使いにくさ
さて、フンコロガシといえば自動採取機能。
これ、一度体験したらやめられませんよね。
放浪モードにして囲いの中で自由に歩かせておくだけで、フンや腐った肉を勝手に肥料やオイルに変えてくれるんだから、控えめに言って神仕様。
ただ、便利さと同じくらい「ちょっと不便…」と感じるところもあるんです。
たとえば、囲いを作り忘れて放浪モードにしたまま放置したら、気付いた時には拠点の外までお散歩してたり。
「おいおい、どこ行った!?」って焦りますよ。
僕の友人も、「一晩で囲いから消えた」って嘆いてました。
そして、インベントリがパンパンだと自動採取が止まるのも盲点なんです。
肥料やオイルをこまめに回収しないと、せっかくの効率が台無し。
このあたり、「定期的なチェックは面倒だけど必須だな」と感じる瞬間です。
餌選びに迷うことのリアル
フンコロガシの餌問題、地味に悩みません?
何でも良いってわけじゃなく、「大型フン」「中型フン」「小型フン」、そして「腐った肉」が使える。
でも、どれを優先するかは悩みどころ。
僕は最初、インベントリに適当に全部突っ込んでたんです。
でも、「大型フン」のほうがテイム効率も肥料変換効率も高いから、畑で大型恐竜を育ててフンを回収するルーチンができました。
一方で、腐った肉も代用にはなるんですが、フンに比べると変換効率が落ちるのがもどかしい。
しかも、餌箱(Feeding Trough)から直接食べることができるのは腐った肉だけ。
フンは直接インベントリに入れてあげないとダメ。
この仕様、地味に忘れがちですよね。
「一回でも切れると生産ストップ、また一からやり直し」ってことになるんで、在庫管理が意外と大事です。
ステ振りで後悔した体験談
あ~、これ語らせてほしい。
フンコロガシのステ振りって、最初は「体力? 移動速度? 攻撃力もあり?」なんて欲張っちゃうんですが、実際やってみて思うのは、「重量」に全振りが正解だなってことです。
僕は過去にスタミナとか体力にも振ったことがあるんですが、フンコロガシは基本、囲いの中で動かすし、戦わせることもない。
だから攻撃力も移動速度もほぼ無意味。
レベルアップ時はとにかく重量重視で、いっぱいフンや腐った肉を入れておく方が絶対効率いいです。
このへん、いろんなサイトや攻略情報見ても「重量に集中!」ってアドバイス多いので、僕みたいに迷ってる人は素直に重量に振っちゃいましょう。
後悔したくないなら、マジでこれ一択です。
肥料作らない場面で焦る気持ち
さて、せっかく苦労してテイムしても、なぜか肥料作らない――この現象、あるあるですよね。
僕も最初にやらかしました。
「インベントリ空なのに、なんで?」と焦った経験、あなたにもあると思います。
原因はいくつかあって、まず「放浪モードにしてない」ケース。
ARK: Survival Evolvedだと、放浪モード必須です。
逆にARK: Survival Ascendedなら、放浪モードいらないパターンもあるので、プレイしてるバージョンをちゃんと確認しましょう。
あとは、餌やフンが入ってないとか、インベントリがいっぱいとか、地形にはまって動けなくなってるとか……。
一度持ち上げて場所変えたり、余分なアイテム捨てたりすると、だいたい直ります。
バグっぽい時もあるので、「何やってもダメだな」って思ったら、拠点の地形や囲いの構造も見直してみるのが吉です。
囲いを作る時に注意したポイント
囲い作りもなかなか奥が深いんですよ。
僕がやらかしたのは「狭すぎてフンコロガシ同士が重なって管理できない」「隙間から脱走する」ってパターン。
おすすめは、小型の恐竜用ゲートや木の柵(Fence Foundation)で囲って、最低でも頭数分のスペースを確保。
柵の高さは1マスで十分な場合が多いですが、不安なら2マスにしてもOK。
隙間ができそうなら、恐竜用ドアフレームで補強すると安心感あります。
囲いの中にはアクセスしやすい扉や通路を用意。
回収や補充の動線を考えて作ると、あとあと楽になりますよ。
「囲いの近くにコンポストや保管箱を置くと超便利」ってのも、実際にやってみて良かった工夫です。
場所選びで失敗した話
最後に、「フンコロガシの設置場所はどこがいい?」問題。
これも地味に悩むところで、僕は拠点の端っこに適当に囲いを作ったら、思いっきり管理しにくくて後悔したことがあります。
理想はやっぱり「畑やコンポストの近く」ですね。
資源の回収も楽だし、餌やりや肥料の運搬の手間も省けます。
屋内や壁に囲まれた場所にしておけば、敵の心配も減るし、雨風もしのげます。
あと、ゲートや扉付きの囲いにすると、迷子や逃走防止にもなります。
「どうせなら作業効率も安全も両立したい」って人は、設置場所選びからしっかり計画すると失敗が減るはずです。
ちなみに、僕の友人は「設置場所が遠すぎて、途中でフンコロガシ見失った」ってぼやいてました。
何はともあれ、管理しやすさを最優先にするのがおすすめですよ。
私が語るARKのフンコロガシ運用のコツ
・持ち方と移動のちょっとしたコツ
・持てない時に直面した問題
・放浪モードの活用で学んだこと
・囲いの広さや構造の悩み
・理想的な設置場所の見極め方
・効率を意識した日々の管理術
・運用を続けて分かった注意点
・ARKのフンコロガシについてのまとめ
持ち方と移動のちょっとしたコツ
ARKでフンコロガシを拠点まで運ぶって、地味だけど結構神経使う場面ですよね。
最初に洞窟で見つけて「よっしゃ!」と思った瞬間、どのルートで連れて帰ろうか…って悩む人は多いはず。
僕も何度も洞窟内で右往左往しました。
まず、フンコロガシ自体はサイズが小さいから、プレイヤーが直接持ち上げることもできるし、「アルゲンタヴィス」や「プテラノドン」みたいな飛行生物に掴ませて運ぶのもアリ。
ただ、注意したいのは、持ち上げた瞬間に足元の地形を確認すること。
洞窟の出入り口や段差、拠点までの道中で、思わぬ場所にひっかかったり、場合によってはそのままフンコロガシが地面にめり込むバグなんかも起きたりする。
僕のおすすめは「一度外に連れ出してから、安全な広場まで持っていく」スタイル。
途中で落とした時は必ず周囲をチェック。
焦って進めるより、ちょっと慎重なくらいがちょうどいいです。
「目的地に着いたら、囲いの中までちゃんと運んで扉を閉める」、これが基本中の基本ですよ。
持てない時に直面した問題
フンコロガシ、どうやっても持ち上げられない…これ、初心者あるあるじゃないですか。
実際僕も最初、「なぜだ!?」って悩んだ経験があります。
その時調べて分かったのが、プレイヤーが直接持ち上げる場合は重量制限はないんですよ。
でも、恐竜や飛行生物で持つときは「その生物がフンコロガシを持ち運べる対象かどうか」が超重要。
「アルゲンタヴィス」や「プテラノドン」ならOKだけど、「トリケラトプス」や「パラサウロロフス」だと持てない。
あと、地形がゴチャついた場所や洞窟の段差、壁際ではどうしても操作が難しい時もあります。
「できるだけ開けた場所や平らな地面で作業する」のがトラブル回避の鉄則。
ちなみに、「インベントリに荷物が多すぎると持てない?」と思いがちですが、フンコロガシの場合、インベントリの重さは直接影響しないので、必要以上に焦らなくても大丈夫。
とはいえ管理しやすさのため、インベントリ整理は習慣にしておくと後々ラクですよ。
放浪モードの活用で学んだこと
フンコロガシの醍醐味の一つが放浪モードで自動的に肥料やオイルを作ってくれること。
これ、初めてやったときは本当に感動しました。
ただし、ここにもいくつか落とし穴があるんです。
「ARK: Survival Evolved」の場合、放浪モードに設定しないと自動生産が始まらないんですよね。
で、これを知らないまま「なんで肥料作らないんだろう」と悩んでいた時期もありました。
逆に「ARK: Survival Ascended」だと、放浪モードじゃなくてもインベントリにフンや腐った肉が入っていれば生産OKなので、プレイしているバージョンによって管理の仕方が変わるのも注意点。
僕が特に気をつけているのは、「放浪モード中は必ず囲いの中で!」ということ。
これ、忘れるとあっという間に拠点の外にお散歩しに行って、二度と戻ってこない…なんて事態になるので要注意。
「必要がなくなったら放浪モードはオフ」、この意識が大事です。
囲いの広さや構造の悩み
正直、フンコロガシ用の囲い作りは何度も試行錯誤しました。
狭すぎると中でごちゃつくし、広すぎると管理がめんどくさい。
ベストなバランスを探すのが意外と大変なんですよね。
僕の実体験から言うと、最低でもフンコロガシの頭数分のスペースは必要。
複数体飼う場合、互いに重ならないように配置するのがコツ。
柵やゲートは木製でも石製でもOKですが、「隙間から脱走しないか」だけは要チェック。
隙間が心配なときは「恐竜用ドアフレーム」を使うと、抜け道防止にめちゃくちゃ役立ちます。
扉やゲートはアクセスしやすい位置に2か所くらい設置しておくと、餌やりや回収作業が圧倒的に楽です。
そして囲いの近くには「コンポスト」や「保管箱」などをセットして、資源の管理効率もアップさせましょう。
作業動線まで意識すると、面倒な手間がぐっと減りますよ。
理想的な設置場所の見極め方
拠点作りで意外と悩むのが、フンコロガシの設置場所。
最初はなんとなく空いたスペースに置きがちですが、実際には畑やコンポストの近くがベストだと気づきました。
理由は単純で、資源回収や餌の補充、肥料の運搬がとにかく楽。
もし屋内や壁で囲まれた場所なら、敵や環境ダメージの心配も激減します。
迷子や逃走防止には「ゲートや扉付きの囲い」も欠かせません。
僕がやった失敗例は「拠点の端っこに置いたら、移動や作業がめんどくさくなった」パターン。
それ以来、必ず中心部や作業スペースの近くに設置するようになりました。
環境次第では屋外でもOKですが、やっぱり安全・快適さのバランスは大事ですね。
効率を意識した日々の管理術
「効率よく管理したい!」って思う人、絶対多いですよね。
僕も最初は「どうしたらラクに回せる?」と工夫しまくりました。
まず、「フン」や「腐った肉」は常にストックしておくことが基本。
畑の近くや恐竜小屋の横でフンを回収できるようにしておけば、餌切れで生産ストップなんてことも防げます。
複数体のフンコロガシを飼っている場合、「餌箱(Feeding Trough)」も活用してみてください。
腐った肉は餌箱経由で補充できるので、まとめて管理できて超便利。
ただし、フンは直接インベントリに入れる必要があるのは忘れずに!
作業ルーチンとしては、「毎日インベントリチェック」「フンや腐った肉の補充」「肥料の回収と保管」――これだけでOK。
一覧にするとこんな感じです。
【日々の管理チェックリスト】
| 管理項目 | ポイント |
|---|---|
| 餌やり | 腐った肉は餌箱、フンは直接インベントリ |
| インベントリ確認 | 肥料で一杯になってないか毎日チェック |
| 回収作業 | 肥料は定期的に保管箱やコンポストへ |
| 囲いの状態確認 | 脱走や迷子防止のためゲート・扉の確認 |
これをルーチンにするだけで、グダグダにならず管理できますよ。
運用を続けて分かった注意点
運用を重ねると、トラブルや落とし穴も見えてきます。
僕が一番焦ったのは「放浪モードのまま外に出てしまって見失った」とき。
こういう時は、囲いを二重にして出入口を減らすとか、定期的に場所を確認することが大切。
また、「餌切れで生産ストップ」「インベントリ満タンで肥料が増えない」「地形バグにはまって身動きできなくなる」――このあたりも油断大敵。
だからこそ、「囲い・餌・回収・囲いチェック」この4点セットを守っておけば、ほとんどの問題は防げます。
ちなみに僕の知り合いは「放浪モードで迷子になったフンコロガシが、近くの敵生物に襲われてた」という話もありました。
安全面も含めて、「管理=リスクヘッジ」だと思って、面倒くさがらずにこまめなチェックを習慣にしましょう。
これでフンコロガシ運用、かなり安定して回せるはずですよ。
ARKのフンコロガシについてのまとめ
・ARKのフンコロガシは洞窟で受動テイムが基本である
・大型フンを優先して使うとテイム効率が上がる
・テイム時は周囲の敵生物を排除する必要がある
・腐った肉も餌として利用できるが効率はやや低い
・餌やフンがインベントリにないと肥料生産が止まる
・放浪モードはバージョンによって必要かどうか異なる
・囲いを作る時は頭数分の広さと隙間防止が重要である
・餌箱は腐った肉のみ対応しフンは直接補充が必要だ
・持ち上げ移動はアルゲンタヴィスやプテラノドンが適している
・設置場所は畑やコンポストの近くが便利である
・ステ振りは重量重視で振るのが正解だ
・インベントリが満タンだと生産が止まるので定期的に回収する
・囲いの出入口や構造も脱走・迷子防止で工夫する必要がある
・地形や段差で持てない時は平坦な場所を選ぶべきである
・毎日のインベントリ・餌チェックをルーチンにすると管理が楽になる
・放浪モード中は必ず囲いの中で運用すべきである
・肥料作らない時はバージョン・餌・囲い・バグなど多角的にチェックすることが大事だ